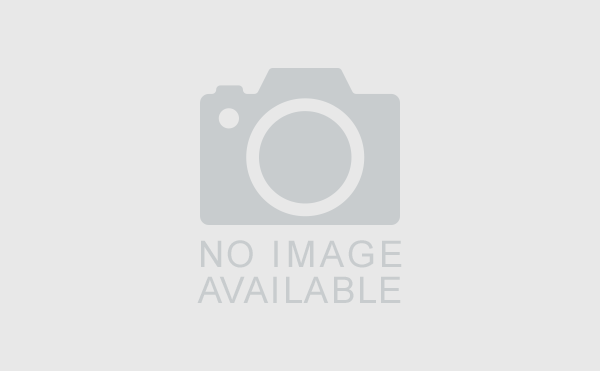人事考課の評価誤差(エラー)
人事評価をする際、どういう基準で評価するのかを4つに分けて説明。またそれでも起こる7つの評価の失敗(誤差)について理解する。そんなんある?というよりかは、そうなることは予想できるものが多く、実感できる、ただ、漢字による勘違いを失くすように違和感があるものだけは確認しておいた方がいい。
- 総合評価
総合評価。これは言葉通り。全体的に見て…80点みたいな評価。これだと主観が入る場合も多いのでは?…
- 分析評価
分析とは「スピード」は?「範囲}は?といった評価基準を決めて評価する。
- 絶対考課
基準を設ける、例えばここまでやったら標準やねといったもの。
- 相対考課
Aさんはやっているけども、Bさんはやっていないのように、比較対象を作るイメージ。
評価が失敗する7つの理由とは何か
- ハロー効果
ハロー効果って確か、その人が持つ優れた性質に、意見がひっぱられて、この人がいうんやったら、あっているのでは?というような感覚を持つこと。つまりは優れた何かを持っている人は、ここが優れているなら、こっちも優れているだろうという風になること。
- 中央化傾向
真ん中によってしまうということ。気遣いなどで起こってしまう現象。
- 寛大化傾向
「悪いかいいか」で言うと、いいにしておいた方がいいのではという心理。または、判断力がない人がとりあえず…といい評価をしている可能性。
- 逆算化傾向
最終評価から逆算して考える評価。この人を昇進または役職から外したいからという理由で評価をする傾向。
- 論理的誤差
例えば、「交渉力」と「コミュニケーション」が似ているから両方評価するなど、こっちができているから、こっちもできているはずといった評価をしてしまう。
- 対比誤差
誰と対比するかというと、評価者と比べて対比してしまい評価してしまう誤差。
- 近接誤差
何が近いかというと、時間的なもの。直近で起こったことを評価してしまうという誤差
まとめ
評価の中では、「分析評価」が勘違いしやすいのではと思った。「速さ」「広さ」「深さ」といった要素を分ける方が、公平な評価が出来そう。だけど、この7つの誤差はあり得る話だと思う。悪用することで、組織や意見の偏り、派閥みたいなものが起りやすくなりそう。中央化が起ってしまう理由などはなるほどなと思うし、対比、近接は何と対比か、何が近接かを間違えなければいいと思う。